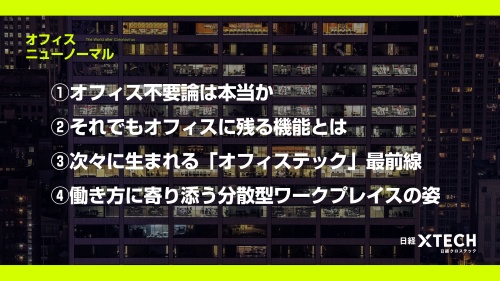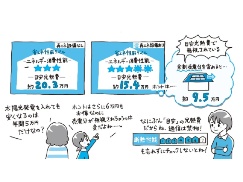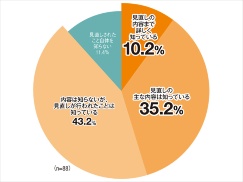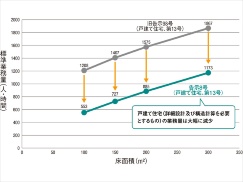目の前にあったのは、もぬけの殻のオフィスだった。
今、多くのビジネスパーソンが次のような疑念を抱いているに違いない。誰も出社しないオフィスなんて、必要なのか──。
東京・田町。サービス産業の生産性改善サービスを手掛けるベンチャー、クリップラインで取締役を務める遠藤倫生も、眼前の空白を前にそう思った。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令翌日の4月8日、同社は全社員の完全在宅勤務を開始。出社率は限りなくゼロに近くなった。遠藤が出社したその日も、会社の指示通り誰も出社していなかった。
港区の一等地に180坪。約80人 が働くこの空間に、同社は月額500万円の賃料を支払っていた。引っ越してきたのは1年半前。それまでの雑居ビルと比較して賃料は2.5倍に膨らんだ。それでも株主などからの「好立地で新しいオフィスは採用に絶大な影響がある」とのアドバイスで移転を決めた。
ただし、遠藤は「もうその価値はない」と踏んだ。
「当然の発想だと思います。誰も来ないオフィスに500万円は払えませんから」
完全在宅勤務を始めてすぐのこと。遠藤は社長の高橋勇人にこう切り出した。「このオフィス、解約しませんか」。高橋も考えは同じだった。遠藤を責任者とし、すぐに移転計画をまとめるよう指示した。それから約10日後、同社はオフィスの解約を決定した。
遠藤が出社率などから試算した「コロナ後に必要なオフィス面積」は、たった60坪。現状の3分の1に過ぎなかったからだ。
クリップラインだけではない。多くのITベンチャーが同様の試算をし、オフィスの解約を既に通知し始めている。一般的にオフィス賃貸契約は半年前の解約予告が必須であることから、今年、秋から冬にかけて、ベンチャーの移転ラッシュが起こるだろう。いずれも、オフィスを縮小する方向だ。
新型コロナウイルスによって、多くの企業がリモートワークを採用し、そのうちの少なくない割合の企業が、在宅と出社による勤務を混ぜるような働き方に移行している。日立製作所が2021年4月から、社員3万3000人のうちの7割を対象に週2-3日の在宅勤務を採用すると発表しているように、「半分在宅」の流れは一般化していくだろう。
その時、オフィスに必要な価値・機能とは何か。本連載「オフィス・ニューノーマル」では、文字通り、今後のオフィスにおける新常態を考えていく。
明らかにしたいことは大きく4つある。(1)現状のオフィスに対する事業会社の動きや今後のオフィス需要の変化、(2)それでも残るオフィスの機能、(3)次々に生まれる「オフィステック 」の最前線、(4)これからの働き方に寄り添う分散型ワークプレイスの姿、である。
まずは(1)について、より詳細に見ていきたい。クリップラインが解約通知を出すまでの流れや、他のベンチャーがオフィス解約を意思決定した例を、次ページで紹介する。